生命保険がおすすめの理由を解説!どれがいいのか選び方を教えます
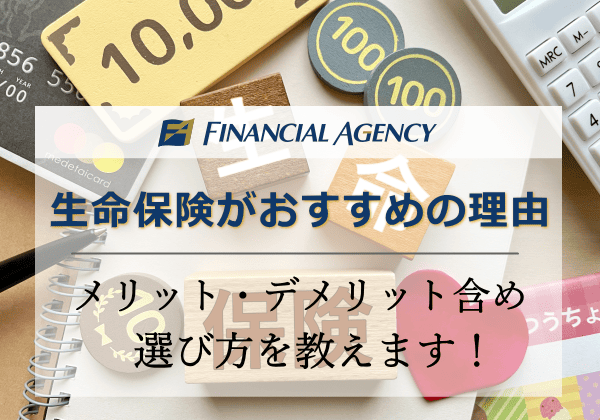
私たちのお客様とお話しすると、「生命保険はどれがいいのか正直分からない..。」「生命保険は難しい…。」という声をよく聞きます。
万が一の事態に備える「生命保険」ですが種類や商品が多く、比較しても分からないと悩む方も少なくありません。
生命保険にはさまざまなタイプがあり、年代やライフステージによって最適な保険は異なります。
そこで本記事は生命保険がおすすめな理由と、最適な選び方を解説します。
生命保険の種類や保障内容、加入のメリット・デメリットなども詳しくお伝えするのでぜひ参考にしてみて下さい。
保険の加入や見直しを検討している方は、これを機に自分や家族にぴったりの生命保険を探しましょう。
生命保険とは?

生命保険とは、万が一の際に自分や家族の生活を守るために備えておく保障の仕組みです。
私たちは病気やケガなど、思いもよらない出来事に遭遇することがあります。
仮に一家の主が事故や病気で突然亡くなった場合、収入がなく経済的に苦しくなる、子どもの教育資金が確保できないなど。
そうした不測の事態が起きた場合でも、生命保険に入っていれば生活費が保障されます。
経済的リスクに備える手段である生命保険には「死亡保険」という認識がありますが、広く言うと保険全般を指すことも。
生命保険には医療保険や介護保険、がん保険、年金保険、学資保険などがあり、商品によって保障内容や加入条件が異なります。
生命保険の仕組み
生命保険は時として自分が払った保険料よりも、受け取れる金額が多くなることもあります。
これは契約者が保険料を負担し合い、それを財源として誰かの保険金を捻出する「相互扶助」から成り立っているためです。

(※画像引用元:生命保険協会|生命保険の仕組み)
一人で支払う保険料は微々たる金額かも知れませんが、大勢が支払うことによって多額の保険金を確保できます。
相互扶助の仕組みによって、万が一の時も安心して保険金を受け取れるよう万全の備えができるという訳です。
生命保険の主な種類と保障内容
生命保険には、大きく分けて3つの種類があります。
生命保険の種類
・死亡保険
・生存保険
・生死混合保険
上記に分類されない「その他の保険」もあります。
生命保険にはどのような種類があるのか、詳しい保障内容なども見ていきましょう。
死亡保険

「死亡保険」とは、被保険者が死亡もしくは所定の高度障害状態に該当した時に支払われる生命保険です。
「高度障害状態」とは?
両眼の視力を完全に失った状態や、両上肢もしくは両下肢を失ったまたはその用を全く永久に失った状態などを言います。
(引用元:生命保険文化センター|生命保険に関するQ&A)
死亡保険に入っていれば、自分に万が一のことがあった場合でも葬儀費用や家族の生活費を補填できます。
死亡保険の種類
・定期保険
・終身保険
・収入保障保険
定期保険
「定期保険」は「5年」「10年」など保険の契約期間が定められている生命保険です。
保険料は掛け捨てであることがほとんどで解約払戻金はないか、あってもごくわずかです。
貯蓄性はありませんが保険料が安い、高額な死亡保障を付けられるなどがメリットと言えるでしょう。
終身保険
「終身保険」は、保障が一生涯継続する生命保険です。
保険料は契約時から一定であり、一定期間で払い込む「有期払い」と終身に渡って支払う「終身払い」があります。
保険期間に解約すると解約返戻金が受け取れるようになっており、貯蓄機能を兼ね備えている点がメリットです。
収入保障保険
「収入保障保険」は「毎月15万」など一定の金額を保険期間が終わるまで受け取れる仕組みです。
保険期間が経過するとともに保険金総額が減るのが特徴で、その分保険料も安く設定されています。
年金形式で毎月受け取る以外にも一括受け取りを選択することも可能ですが、受取総額が少なくなる点がデメリットです。
生存保険

「生存保険」とは、被保険者が満期日以降に生存している時に支払われる生命保険です。
生存保険は生活資金などの目的として加入することが多く「個人年金保険」「学資保険」などがあります。
生存保険の種類
・個人年金保険
・学資保険
個人年金保険
「個人年金保険」とは、老後などに必要な資金を補完する目的で加入する保険です。
一定期間まで保険料を払い込んだ後、受取開始時期になると年金形式もしくは一括で受け取れる仕組みです。
老齢年金に上乗せする形で受け取れるため、貯蓄性が高く老後資金の準備になる点がメリット。
「定期型」と「変額型」や円建て・外貨建てなど、運用方法や受け取り期間などさまざまな選択肢があります。
学資保険
「学資保険」は、子どもの教育資金を準備するための保険です。
毎月決まった保険料を支払うことで、定めた時期になると計画的に保険金を受け取れます。
貯蓄型の学資保険では、保険期間中に契約者が亡くなった場合などに保険料の払い込みが免除になる点も特徴。
商品によって保険料や払込期間などが異なっており、返戻率の高い学資保険を選ぶことが大切です。
生死混合保険

「生死混合保険」とは「死亡保険」と「生存保険」を組み合わせた生命保険です。
契約者が死亡もしくは高度障害状態の場合には死亡保険が支払われます。
ある一定期間まで生存していた場合は「生存保険」として保険金が受け取れる仕組みです。
生死混合保険の種類
・養老保険
養老保険
生死混合保険の代表的な「養老保険」は、死亡保障と貯蓄の両方が備えられる生命保険です。
保険期間中は死亡保障で備えられる上に、そのまま満期を迎えたら保険金を受け取れる仕組みです。
「死亡保障=満期保険金」となるため、万が一のことが起こらなくても同額の金額を受け取れる点がメリットです。
また満期を迎えた場合に保険金を受け取らずに据え置くことで、わずかながら保険金を増やせる可能性があります。
しかしながら終身保険や定期保険と比較すると保険料が割高になる、途中で解約しにくいなどのデメリットも。
満期保険金を受け取った後は死亡保障がなくなるため、新たな保険加入が必要なケースもあります。
以上の3タイプが生命保険の代表的な種類です。
これら以外にも、生命保険ではさまざまなリスクに対応する保険があります。
【その他の保険】
| 医療保険 | 病気やけがで入院・手術などした場合の保険 |
| がん保険 | がんと診断された場合に給付される保険 |
| 介護保険 | 所定の要介護状態に該当した場合の保険 |
| 就業不能保険 | 病気やけがで働けなくなった場合の保険 |
病気やけがで入院・手術した際に給付される「医療保険」や「がん保険」など、幅広いリスクに備える保険商品があります。
保険にはさまざまな種類が存在するため、自分の目的に合った保険を選ぶことが大切です。
「生命保険」と「医療保険」は違う商品なの?
万が一の時のリスクに備えるという点では同じですが、厳密にいうと違う分類です。
「生命保険」⇒死亡もしくは高度障害になった際の保障が目的
「医療保険」⇒病気やケガの治療に対する保障が目的
死亡保障付きの医療保険もありますが、生命保険の保障額と比較すると少額であるケースがほとんどです。
また生命保険では入院や治療費が対象外になることもあるため、必要に応じてそれぞれに加入するようにしましょう。
ライフスタイルの変化で生命保険がおすすめの理由とは?

生命保険文化センターの調査によると、生命保険に加入している割合は次の通りです。
【生命保険加入率】
| 男性 | 77.6% |
| 女性 | 81.5% |
(引用元:生命保険文化センター「リスクに備える生活設計」※2022年度「生活保障に関する調査」)
男性で77.6%、女性で81.5%となっており、男女ともに約80%の方が加入していることが分かります。
年代別に見ていくと、男女ともに50歳代で最も加入率が高くなっています。

20歳代は男女ともに50%ほどですが、30歳代になると80%を超えることが分かります。
30歳代から40歳代は、結婚などでライフスタイルが大きく変化する年代です。
お子さんがまだ小さい家庭も多く、万が一のことがあった場合に備えて加入するケースが多いことが分かります。
その後50歳代をピークに、徐々に加入率が減っていきます。
生命保険がおすすめの理由

万が一の時の備えとしておすすめの生命保険ですが、一方で「生命保険が不要なのでは?」と考える方もいるのではないでしょうか。
まして元気なうちは「病気や死ぬのはずっと先のこと」と感じる方も少なくありません。
日本では「医療費3割負担」「高額療養制度」などの公的保証が充実しています。
しかし先進医療などの自由診療を受ける場合は、公的な医療保障ではまかなえないことも少なくありません。
それらを踏まえて、生命保険がおすすめの理由について見ていきましょう。
万が一のリスクに備えられる
病気やけがなどをしたり一家の大黒柱が予期せず亡くなった場合、収入が途絶えてしまい生活が困難になる可能性があります。
こうした突然の事態は予測できないため、経済的な損失額が大きければ貯蓄だけで補うのは難しいでしょう。
生命保険はいつ起こるか分からないリスクに備える方法であり、万が一の時に対応できるようにする手段です。
たとえ起こる確率が低くても大きな費用がかかってしまうものこそ、生命保険で備えるべきものだと言えるでしょう。
通院費・入院費が保障される
病気やけがをした場合、医療保険に加入していないと治療費を自分で賄う必要があります。
特に入院や手術が必要になると高額の治療費が発生するため、貯蓄を取り崩すケースも少なくありません。
貯蓄が少ない方などは、入院で収入が途絶えると治療費を補うのが難しくなることも考えられます。
そんな不測の事態が発生した時でも、医療保険に入っていれば治療費を保険金で賄うことが可能です。
収入がない場合でも、就業不能保険などに加入していれば家族の生活費が保障されるので万が一の時も安心です。
老後や将来の貯蓄にもなる
「なかなか貯蓄が増えない」「計画的に貯蓄できない」という方も多いのではないでしょうか。そのような方におすすめなのが、貯蓄性のある生命保険です。
貯蓄型保険は、万が一に備えながら貯蓄もできる保険のことです。
その名の通り保障機能と貯蓄機能を兼ね備えており、安定的に貯蓄したい方におすすめ。
貯蓄が苦手な方でも保険料として自動的に引き落とされるため、無理なく資産作りができます。
払った保険料を無駄にしたくないという方や、掛け捨て型の保険に加入したくない方は、貯蓄型保険を検討してみて下さい。
自営業の人は必要性が高い
日本の公的年金は、全ての人が加入する「基礎年金」と会社員が加入する「厚生年金」の2階建てです。
基礎年金は満額¥816,000であり、月額にすると¥68,000なので(令和6年4月分から)、公的な年金制度だけで老後の生活費を補うのは困難だと言えるでしょう。
そう考えると自営業やフリーランスの方の場合、万が一の際の生命保険の必要性が高いのは言うまでもありません。
また非正規雇用で働いてきた方などは退職金もないため、ますます生命保険の必要性が高まるでしょう。
※参考:日本年金機構|老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・年金額
生命保険に加入しないリスクとは?

さまざまなリスクに対応できるおすすめの生命保険ですが、加入が義務付けられている訳ではありません。
そう考えると「今急いで加入しなくてもよいのでは?」と考える方もいるのではないでしょうか。
では生命保険に加入しないとどういうリスクがあるのかを見ていきましょう。
生命保険に加入しないリスク
・万が一の際に残された家族が生活できない
・病気やけがで医療費がかかる
・収入が途絶える
・子供の教育費を払えない
・老後の生活費が足りない
家族がいる方の場合、万が一の際に残された家族が生活できなくなってしまうかも知れません。小さいお子さんがいるご家庭であれば、生活費だけでなく教育費の心配もあります。
また独身者であっても病気やけがで医療費がかかる上に、休業期間の収入が途絶えるリスクも。
特にがん治療などはある程度の時間が必要である上に、先進医療を受けた場合は莫大な医療費がかかってくるでしょう。
予期せぬ病気やけがで動けなくなってしまうことは、誰にでも起こりうるリスクです。
そのような事態になっても、生活に困らないだけの蓄えはありますか?
もし十分な蓄えがないという方は、万が一の際の生命保険への加入を検討してみる必要があります。
生命保険のメリット・デメリットを解説
万が一の備えとしておすすめの生命保険ですが、中には「貯蓄の方がいいのでは?」と考える方もいるかも知れません。
もちろん貯蓄は万が一の際の備えとしてメリットがありますが、生命保険にも多くのメリットがあります。
では生命保険に加入するメリットとデメリットを比較してみましょう。
生命保険のメリットとは

生命保険のメリット
・万が一の際の保証ができる
・所得税・住民税の対策になる
・相続税の対策になる
・資産運用にもなる
生命保険に加入することで、万が一何かあった際のリスクに備えることが可能です。
葬儀費用をはじめ残された家族の生活費などの準備ができるため、経済的なリスクを回避できます。
本人が高度障害状態になった場合であっても、死亡と同等の保険金を受け取ることができます。
入院や手術が必要な場合であっても、医療保険やがん保険に加入すれば給付金で賄うことも可能です。
生命保険の保険料は控除の対象となるため、所得税や住民税の負担が軽減されるメリットもあります。
年末調整や確定申告で生命保険料控除を申請すれば所得から一定額の税金を控除できるので、有効な節税対策となるでしょう。
また生命保険の相続には非課税枠が適用されるため、相続税対策にもなります。「500万円×法定相続人の数」まで非課税となるため、非課税枠を増やして相続税を回避する手段としてもおすすめです。
それ以外にも生命保険に加入することで、資産運用につながるケースもあります。
外貨建て保険や変額保険といった投資信託の性格を持つ保険に加入することで、解約返戻金を増やすことも期待できます。
もちろんリスクは0ではありませんが、死亡・高度障害保険金には最低保証があるため投資よりもリスクを少なくできる可能性があります。
生命保険のデメリットとは
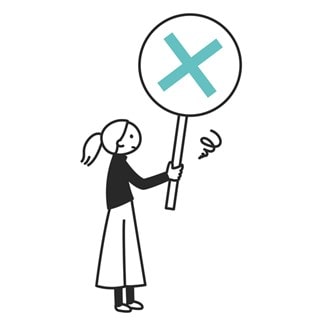
生命保険のデメリット
・インフレのリスクがある
・早期解約すると損する
・保険料の負担がある
生命保険の多くは契約時に保険金の額が決まります。そのためインフレが起こった場合、実質的な資産価値が目減りするリスクがあるため保障の価値が下がってしまうことも。
そうならないためにはインフレに強い金融商品へ投資したり、定期的に契約内容を見直すことも有効です。
保険金の一部が戻ってくる生命保険の場合は、途中で解約すると返戻金が少なくなったり元本割れするリスクが高くなります。
特に貯蓄性の高い保険などは短期間で解約すると損するため、計画的に契約するようにしましょう。
生命保険では万が一の保障によって安心を手に入れられますが、その代わり決められた保険料を支払わなければなりません。
当たり前の話ですが、保険料が生活費を圧迫しないように無理のない金額設定で支払うことが大切です。
生命保険の選び方3ステップ!

生命保険へ加入する必要性やメリット・デメリットなどについて解説しました。
しかしいざ保険を選ぶとなった場合「どうやって選んだらいいの?」と疑問に思う方も多いことでしょう。
自分に合った保険の種類を見つけるためにも、選び方のポイントをわかりやすくまとめてみました。
ステップ①:「目的」と「期間」を決める
生命保険にはさまざまな種類があるため、まずどのような保障が必要かを明確にすることが大事です。
どれがいいかを考える前に、そもそも生命保険はあなたにとってなぜ必要なのでしょうか?
何のために生命保険に加入するかによって、おのずと必要な保障の種類や期間が決まってくるでしょう。
代表的な保障ニーズと、それに対する主な保険についてまとめてみました。
【代表的な保障ニーズと主な保険】
| 保障ニーズ | 保険の種類 |
| 万が一の死亡・高度障害に備えたい | 定期保険・終身保険 |
| 病気やけがの治療費に備えたい | 医療保険 |
| がんに備えたい | がん保険 |
| 病気やけがの収入減少に備えたい | 収入保障保険 |
| 介護に備えたい | 介護保険 |
| 老後の生活費に備えたい | 個人年金保険 |
死亡や高度障害になった場合に備える「死亡保障」には「定期タイプ」と「終身タイプ」があります。
定期タイプ
「定期タイプ」は一定期間を保障するタイプで保険料が安い点がメリットです。
しかし保険期間が終了した際に更新する場合、保険料が割高になる可能性があるので注意しましょう。
終身タイプ
「終身タイプ」は一生涯リスクに備えられる特徴がありますが、その分保険料が高くなると言えます。
また生命保険は「主契約+特約」という組み合わせが可能です。
主契約に特約というオプションを上乗せすることによって、保障内容をさらに手厚くするというメリットも。
一口に生命保険といってもさまざまな種類があるので、選び方も含めて保険代理店に確認することが大切です。
ステップ②:必要保障額を試算する
希望する生命保険の種類が決まった場合、次に必要な保障額がいくらかを試算しましょう。
保障額を高くすればするほど保険料の負担が大きくなるため、必要な金額をシミュレーションすることが大切です。
必要保障額を試算する方法は「必要な金額-社会保障で受けられる給付金」であり、社会保障制度を差し引いて計算するのがポイントです。
例えば老後の生活費を生命保険で賄う場合は「老後に必要な生活費-公的年金=必要保障額」というように考えます。
必要保障額は家族構成や子供の有無によっても変わるため、十分な試算が必要です。
自分で必要額を試算するのが難しいという方は、ファイナンシャルプランナーに相談するとよいでしょう。
ステップ③:目的に合った生命保険を決める
必要な保障ニーズと期間、保障額が決まった場合、あとはどの生命保険に加入するのかを決めるのみです。
上でもお伝えしたように生命保険と一言で言ってもさまざまな種類があります。
例えば「死亡保険」の場合は、下記の主に4種類から選択できます。
・終身保険
・定期保険
・収入保障保険
・養老保険
また主契約に特約を付けるかどうかによっても保証は大きく変わってくるため、慎重に検討することが大切です。
ファイナンシャルプランナーには無料で相談できるため、自分に合った保険を見つけるためにもぜひ活用してみて下さい。
【年代別】生命保険の選び方

それでは生命保険選び方について見ていきましょう。
ライフスタイルによって必要な保険は異なるため、まずは年代別のポイントを見ていきましょう。
「20代」生命保険の選び方
20代の皆さんの中には、「健康には自信がある」「生命保険など必要ないのでは?」と考える方も多いのではないでしょうか。
実際に20代の保険加入率は男性:46.4%、女性:57.1%となっており、年代別の加入率は最も低いことがわかっています。
引用元:2022(令和4)年度「生活保障に関する調査│生命保険文化センター」
他の年代よりも病気やけがのリスクは比較的ありませんが、20代だからこそ生命保険に加入するメリットはたくさんあります。
20代が生命保険に加入するメリット
・保険料が安い
・資産形成になる
・加入できる選択肢が増える
生命保険は加入時の年齢が若ければ若いほど、基本的に保険料が安くなります。
病気やけがのリスクは年齢が上がるほど高くなるため、20代は安い保険料で加入できるのが大きなメリットです。
貯蓄型の生命保険を選択すれば将来の資産形成としても有効ですし、節税対策にもなります。
また保険によっては健康状態によって加入できないなど条件があるため、健康な20代の方が圧倒的に有利だと言えます。
では20代が加入すべき保険にはどういうものがあるのでしょうか。
【20代の保険】
| 医療保険 | 病気やけがをした場合の治療費を補う保険 |
| 就業不能保険 | 病気やけがで働けなくなった場合の収入減少に備える保険 |
| 個人年金保険 | 公的年金に上乗せする保険 |
20代の場合、死亡や高度障害状態になった場合の死亡保険よりも医療保障に備える保険がおすすめです。
病気やけがをした場合の治療費を補える「医療保険」や、働けなく収入が減少した時に備える「就業不能保険」などがあります。
また公的年金だけでは老後の生活が心配という方には「個人年金保険」がおすすめ。
加入する年齢が早ければ早いほど、掛け金が少額であっても老後の年金はしっかり確保できる可能性が高くなります。
また20代など若いうちから加入した方が返戻率は高くなるため、個人年金保険を検討している方は早めが良いでしょう。
「30代」生命保険の選び方
30代になると結婚や子供が生まれる、またマイホームを持つなどライフステージの変化が起こるケースも多いでしょう。
そうなると家族や子供を守るための生命保険の加入が重要視され、いよいよ本格的に加入を検討する時期です。
実際に生命保険の加入率は男性:81.5%、女性:82.8%となっており、20代とは比較できないほど加入率が増えてきます。
引用元:2022(令和4)年度「生活保障に関する調査│生命保険文化センター」
しかし保険料がかさんで貯蓄ができないのでは本末転倒なので、家計状況に合わせた生命保険を選ぶことが大切です。
30代が加入すべき保険には、次のような種類があります。
【30代の保険】
| 医療保険 | 病気やけがをした場合の治療費を補う保険 |
| 就業不能保険 | 病気やけがで働けなくなった場合の収入減少に備える保険 |
| 個人年金保険 | 公的年金に上乗せする保険 |
| 学資保険 | 子どもの教育資金を準備するための生命保険 |
| 死亡保険 | 死亡もしくは所定の高度障害状態に該当した時に保障される保険 |
30代になると20代の頃よりも病気やけがのリスクが多少高まるため、医療保険や就業不能保険への加入がおすすめです。
一家の大黒柱が働けなくなった場合でも、就業不能保険に入っていれば残された家族の生活費をまかなえるので安心です。
お子さんのいる家庭では、学資保険で教育資金を準備することもポイント。
そろそろ死亡保険で万が一のリスクに備えたいところですが、あれもこれも加入すると家計状況が圧迫されることも。
まずは掛け捨ての割安な死亡保険に加入しながら、将来の必要な資金を早めに確保することが大切だと言えます。
さまざまな保険商品の中からベストな選択をするためにも、ライフプランナーに無料で相談するのも1つの方法です。
「40代」生命保険の選び方
公私ともに充実してくる40代は、ライフステージが変わりやすい時期でもあります。
さらに生活習慣病やがんのリスクなども一気に上昇するため、万が一の時に備える必要性はますます高まってくるでしょう。
そのため20代や30代の頃に加入した保険を見直し、今後のライフスタイルに合ったものに変更するのがおすすめです。
40代における生命保険の加入率は男性86.1%、女性:86.3%となっており、30代よりもさらに加入率が増えています。
引用元:2022(令和4)年度「生活保障に関する調査│生命保険文化センター」
40代が加入すべき保険には、次のような種類があります。
【40代の保険】
| 医療保険 | 病気やけがをした場合の治療費を補う保険 |
| がん保険 | がんと診断された場合に給付される保険 |
| 就業不能保険 | 病気やけがで働けなくなった場合の収入減少に備える保険 |
| 個人年金保険 | 公的年金に上乗せする保険 |
| 学資保険 | 子どもの教育資金を準備するための生命保険 |
| 死亡保険 | 死亡もしくは所定の高度障害状態に該当した時に保障される保険 |
お子さんの学費準備や住宅ローン返済など何かと支出が多い40代ですが、病気の罹患率が高くなるのも現状です。
30代までと比較すると特にがんへの罹患率が高くなり始めるため、がん保険なども検討しましょう。
医療保険にすでに加入している場合は、保障ニーズや予算に応じて保障内容を見直すのがおすすめ。
医療保険には一生涯保障が続く「終身保険」と、一定期間の保障に備える「定期保険」の2種類があります。
保障内容が同じであれば定期保険の方が月々の保険料が安くなりますが、更新後の保険料が高くなるリスクも。
終身保険は契約時点の年齢で保険料が決まるので、若いうちに加入すれば保険料が安くなる可能性もあります。
それぞれにメリット・デメリットがあるため、ご自身のライフプランや家計の状況に合わせた商品を選ぶことが大切です。
「50代」生命保険の選び方
保険への加入や見直しは30代・40代で行うものというイメージをもつ方もいますが、実はそうでもありません。
実際に50代は子どもの独立や親の介護などライフステージが変わりやすい時期であり、それに伴った保険の見直しが必要です。
またご自身の老後に備える大切な期間でもあり、健康状態の面で不安を感じる方も増えてくるでしょう。
50代における生命保険の加入率は男性86.9%、女性:87.8%となっており、全世代で最も高い加入率となっています。
引用元:2022(令和4)年度「生活保障に関する調査│生命保険文化センター」
50代以降が加入すべき保険には、次のような種類があります。
【50代の保険】
| 医療保険 | 病気やけがをした場合の治療費を補う保険 |
| がん保険 | がんと診断された場合に給付される保険 |
| 介護保険 | 介護が必要になった際に備える保険 |
| 就業不能保険 | 病気やけがで働けなくなった場合の収入減少に備える保険 |
| 個人年金保険 | 公的年金に上乗せする保険 |
| 死亡保険 | 死亡もしくは所定の高度障害状態に該当した時に保障される保険 |
50代以降になると病気やけがのリスクがさらに高まるため、医療保険やがん保険の見直しが必要となってきます。
さらに自身の老後について考える時期でもあるので、介護保険で万が一のリスクに備えるようにしましょう。
介護保険は認定を受ければ公的な負担を軽減できますが、それだけでカバーできる訳ではありません。
高齢化社会が加速する中、50代以上の方が介護リスクに備える必要性はますます高まってくるでしょう。
年金や貯蓄などで介護費用を補えるかどうか確認し、必要であれば元気なうちに加入を検討することをおすすめします。
【ライフステージ別】生命保険の選び方
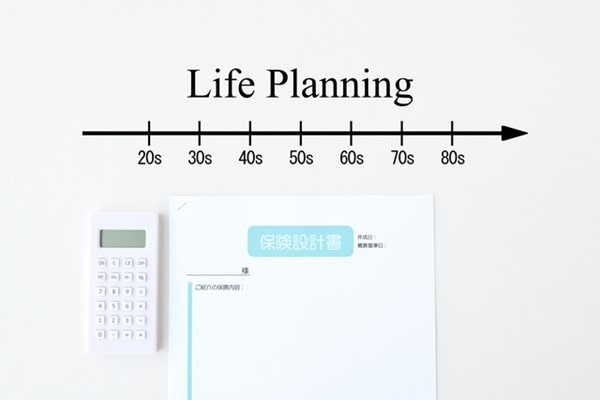
年齢ごとの生命保険の選び方を紹介しましたが、次にライフステージごとの生命保険について考えていきましょう。
結婚やお子さんの誕生など、人生にはさまざまなライフイベントが訪れます。
ライフステージが変わると保障リスクも変化するため、保険の見直しによって必要な保障だけを選択することが大切です。
では主なライフステージにおける生命保険選びのポイントについて見ていきましょう。
「独身(単身)」の生命保険選び方
「独身の場合、生命保険に入る必要がないのでは?」と考える方もいるでしょう。
配偶者や子供がいない場合、高い死亡保障や生活費を補填する必要性はさほど高くありません。
しかし将来的に結婚の予定があったり、もし親がいなくなった場合を考えると生命保険に加入しておくのがおすすめです。
生命保険によって資産形成できる商品もあるので、将来のためにお金を貯めたい方も保険を活用できると言えます。
では独身の方が加入すべき保険には、どういうものがあるのでしょうか。
【独身の保険】
| 医療保険 | 病気やけがをした場合の治療費を補う保険 |
| 就業不能保険 | 病気やけがで働けなくなった場合の収入減少に備える保険 |
| 死亡保険 | 死亡もしくは所定の高度障害状態に該当した時に保障される保険 |
独身・既婚にかかわらず病気やけがのリスクはあるため、医療保険で備えておくのがおすすめです。
公的な医療保険で3割負担とはなるものの、入院や治療でまとまったお金が必要となるケースもあります。
高額療養制度によって一定額を超えた場合は払い戻しされますが、やはり医療保険で備えておいた方が安心でしょう。
ちなみに会社員の方の場合「傷病手当金」という制度があります。
傷病手当金
・病気やけがで働けない場合に支給される
・仕事を休んでから4日目以降の日に対して支給される
・給料の約3分の2が保障される
・支給期間は最長1年6か月まで
傷病手当金は働けない期間の給料が保障される制度ですが、最大3分の2までの保障額なので満額ではありません。
最長1年6か月までなどいくつかの条件があるため、万が一のリスクに備える必要があります。
また自営業者にはそのような制度がないため、治療費や入院費・生活費などを補うための保障を確保することが大切です。
病気やけがで働けなくなった場合に収入の補填となるのが「就業不能保険」です。
同じような商品で「所得補償保険」という商品もありますが、基本的には同じような内容です。
| 就業不能保険 | 生命保険会社が取り扱う商品 |
| 所得補償保険 | 損害保険会社が取り扱う商品 |
主に取り扱う会社が異なりますが、どちらも働けないリスクに備える商品なので独身の方におすすめです。
医療保険・就業不能保険とともに検討しておきたいのが「死亡保険」です。
独身の場合、多額な死亡保障は必要ありませんが、お葬式代や遺品整理なども考え備えておくと安心です。
「夫婦」の生命保険選び方
次に夫婦の保険選びについて見ていきましょう。夫婦には「共働き」「片働き」という2つのスタイルがあります。
共働きの夫婦であればどちらかが亡くなっても自分で働けるため、それほど死亡保障を手厚くする必要がありません。
ただしどちらか一方の収入しかない場合は、死亡保障に加入しておくことが必要です。
また将来的に子どものいる生活を望むかどうかによっても、加入すべき保険は変わってくるでしょう。
家族が増えると生活費や教育費の準備なども必要となるため、新たな保険加入を検討しなければなりません。
妊娠、出産の際も帝王切開などは医療保険で補えるので、妊娠前から加入しておくのがおすすめです。
もし子供を望まない夫婦であれば、次のような保険がおすすめです。
【夫婦の保険】
| 医療保険 | 病気やけがをした場合の治療費を補う保険 |
| 就業不能保険 | 病気やけがで働けなくなった場合の収入減少に備える保険 |
| 個人年金保険 | 公的年金に上乗せする保険 |
夫婦2人の場合、働けないリスクに備える必要があるため、「医療保険」や「就業不能保険」がおすすめです。
貯蓄が苦手な夫婦であれば、老後資金に備えるために「個人年金保険」に加入しておくのがよいでしょう。
個人年金保険では一定額を先取り貯蓄する仕組みとなっており、自動引き落としなどすれば計画的に貯蓄できます。
所得税や住民税の優遇を受けられる可能性もあるなど、さまざまなメリットがある点もポイントです。
月々5,000円〜など気軽にスタートできる保険商品も多いので、公的年金の補填として検討してみて下さい。
「ファミリー」の生命保険選び方
ファミリー世帯においては、子どもが成人するまでの教育費を視野に入れることがポイントです。
教育費は子どもの成長とともに増加するため、小さい頃から備えておくことが大切です。
まず幼稚園から大学まで通う場合の、教育費について見ていきましょう。
【幼稚園から高校まで通う場合の学習費】
| 公立の場合 | 私立の場合 | |
| 幼稚園 | ¥532,177 | ¥1,038,087 |
| 小学校 | ¥2,017,378 | ¥10,974,394 |
| 中学校 | ¥1,626,213 | ¥4,671,589 |
| 高校 | ¥1,787,328 | ¥3,077,235 |
(引用元:文部科学省「学校種別学習費総額の推移」)
【大学を通う場合の学費(昼間部を4年間通った場合)】
| 公立の場合 | 私立の場合 | |
| 大学 | ¥2,332,000 | ¥5,232,400 |
(引用元:「令和4年度 学生生活調査結果」)
教育費には「授業料」「学校納付金」「修学費」「課外活動費」「通学費」などが含まれています。
中学校・高校ではそこまで変わらないものの「小学校」「大学」では大きな費用の違いがあります。
特に教育費がかかるのは大学4年間となっており、国公立では約233万円、私立では約523万円となっています。
大学進学を考えているご家庭であれば、学資保険などで300万円以上は準備しておくのがおすすめです。
子どもの教育費は公立か私立かによっても大きく異なるため、早いうちからシミュレーションしておきましょう。
ファミリー世帯が加入すべき保険には、次のような種類があります。
【ファミリーの保険】
| 医療保険 | 病気やけがをした場合の治療費を補う保険 |
| 就業不能保険 | 病気やけがで働けなくなった場合の収入減少に備える保険 |
| 学資保険 | 子どもの教育資金を準備するための生命保険 |
| 死亡保険 | 死亡もしくは所定の高度障害状態に該当した時に保障される保険 |
ファミリー世帯は万が一のリスクに備えつつも、子どものために貯蓄することが必要です。
特に一家の大黒柱が働けなくなった場合「医療保険」や「就業不能保険」で備えることが大切です。
子どもの年齢が低い場合には学資保険だけでなく「死亡保険」を検討するのもポイント。
死亡保険は子どもが独立するまでの一時的な保障として、定期保険に加入すると保険料負担も大きくありません。
ファミリー世帯は教育費だけでなく住宅費用など何かと出費が多い世帯でもあります。
保険料で家計が圧迫されないように、収入に応じて無理なく払える保険料を設定することが大切です。
「持病がある方」の生命保険選び方
持病がある方の場合、保険会社や商品によって加入の可否や条件が指定されるケースがあります。
そのため一般の方と比べると生命保険の幅が狭くなるので注意が必要です。
持病がある方が入れる生命保険には、次の3種類あります。
【持病がある方の保険】
| 一般の保険 | 不担保期間があるなど条件付き |
| 引受基準緩和型保険 | 持病も保障対象となる |
| 無選択型保険 | 健康状態に関係なく誰でも入れる |
一般の保険
一般的な保険の場合、健康状態によって一定の条件付きであることがほとんどです。
例えば「〇〇の部位において5年間不担保期間あり」などの条件が付き、持病や既往症について保障されないケースです。
それ以外は一般の方と同じ条件なので、他のタイプよりも保険料が安い点がメリットです。
引受基準緩和型保険
「引受基準緩和型保険」は、一般の保険に加入できない方でも入りやすい保険です。
健康状態に関する質問事項が少なく、持病が悪化した場合でも対象になる点がメリット。
持病が再発しても保障される保険なので、万が一の時も安心ですね。
しかし一般の保険よりも保険料が高く、一定期間保障されないなどのデメリットがあります。
無選択型保険
「無選択型保険」は健康状態に関する質問がなく、誰でも加入しやすい保険です。
医師の診査なども必要ないので、持病がある方だけでなく高齢者など誰でも加入できるのはかなり魅力的ですね。
しかし保険料がどのタイプよりも高額であり、一定期間保障されないなどのリスクもあります。
持病をお持ちの方の保険選びは難しいケースが多いので、まずはファイナンシャルプランナーに相談するのがおすすめです。
「掛け捨て型」と「貯蓄型」はどう違う?それぞれのメリット・デメリットを解説
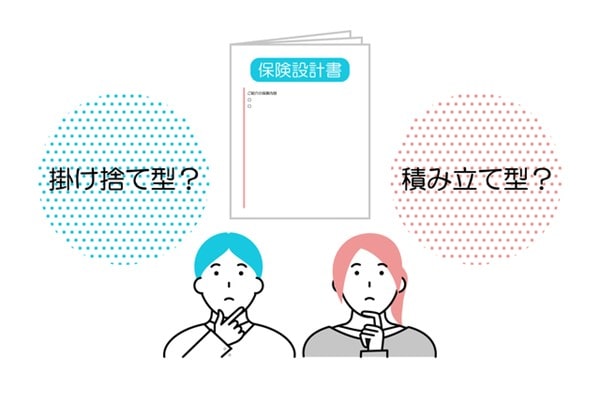
生命保険には次の2つの種類があります。
生命保険の種類
・掛け捨て型
・貯蓄型
それぞれ特徴やメリット・デメリットが異なるため、どういう違いがあるのかを解説します。
これから生命保険を検討している方やどれがいいか迷っているという方は、ぜひ参考にしてみて下さい。
「掛け捨て型」保険とは?4つの種類とメリット・デメリット
「掛け捨て型」とは、決められた契約期間にのみ保険金を受け取れる保険のことです。
契約期間中に当てはまる事案がなければ、支払った保険料は戻ってこない仕組みとなっています。
掛け捨て型保険には、次のような種類があります。
【掛け捨て型保険】
| 定期保険 | 死亡や高度障害状態になった際に、受け取れる保険 |
| 医療保険 | 病気やけがで入院・手術などした場合に備える保険 |
| がん保険 | がんと診断された場合に給付される保険 |
| 就業不能保険 | 病気やけがで働けなくなった場合に備える保険 |
「定期保険」は、「5年」「10年」など一定の保険期間に死亡・高度障害状態になった場合に保険金が支払われます。
保険期間は「更新型」と「全期型」の2パターンあり、「全期型」は期間満了後に更新できません。
「更新型」は満期になると自動更新されますが、年齢によって保険料の見直しが入ります。
【掛け捨て型保険のメリット・デメリット】
| メリット | デメリット |
| ・保険料が安い ・少ない保険料で大きな保障が得られる ・保険の見直しがしやすい | ・一定期間で終了する ・更新時に保険料が上がる ・保険料が戻ってこない |
掛け捨て型保険の最大のメリットは、終身保険と比べて保険料が安いことです。
少ない保険料で大きな保障が得られるため、高額な保険料を支払えない方におすすめです。「10年」など一定期間の保障を手厚くできる上に、満了時に保険を見直しやすい点も魅力です。
ただし掛け捨て型保険は一定期間で保障が終了するため、同じ保障を続けたい場合は更新する必要があります。
年齢によって保険料が再計算される仕組みとなっており、同じ保障内容でも更新時は高くなるケースがほとんどです。
満期保険金や解約返戻金もほとんどないため、保険料が戻ってくることはありません。
とはいっても少ない掛け金で大きな保障が得られる点は、掛け捨て型保険ならではのメリットです。
「貯蓄型」保険とは?4つの種類とメリット・デメリット
「貯蓄型」とは、保障とともに貯蓄の機能も兼ね備えた保険のことです。
満期時や解約時に解約返戻金が受け取れるため、掛け捨て型保険に抵抗のある方にもぴったりです。
万が一の保障を準備しながら貯蓄もできる貯蓄型保険には、次のような種類があります。
【貯蓄型保険】
| 終身保険 | 死亡や高度障害状態になった際に、受け取れる保険 |
| 個人年金保険 | 公的年金に上乗せする保険 |
| 養老保険 | 死亡保険と生存保険の両方の機能を兼ね備えた生命保険 |
| 学資保険 | 子どもの教育資金を準備するための生命保険 |
「終身保険」は死亡や高度障害状態になった際に、受け取れる保険のことです。
「定期保険」が掛け捨てなのに対して、「終身保険」は一生涯保障が続くというメリットがあります。
「個人年金保険」は年金に上乗せして受け取れる保険であり、老後資金の形成を目的としています。
「養老保険」は死亡した際は死亡保険金として、生存している場合は満期保険金として受け取れる保険です。
どちらの場合も同じ金額が支払われる点が特徴で、保険期間が自由に設定できるため目的に応じた使い方がしやすいと言えます。
「学資保険」は子どもが決められた年齢になれば保険金が受け取れるため、資産形成としてもおすすめの保険です。
これらの貯蓄型保険には、次のようなメリット・デメリットがあります。
【貯蓄型保険のメリット・デメリット】
| メリット | デメリット |
| ・保障と貯蓄機能の両方を備えられる ・満期時に解約返戻金が受け取れる ・契約者貸付が利用できる | ・掛け捨て型と比べて保険料が高い ・途中解約で解約返戻金が安くなるリスク ・インフレで価値が目減りする可能性がある |
貯蓄型保険は掛け捨て型よりも割高になりますが、満期時に解約返戻金が受け取れる点がメリットです。
保障だけでなく貯蓄機能があるため、払った保険料が無駄になることがありません。
また保険料の支払いが厳しい場合、「契約者貸付」という制度で解約返戻金の一部を保険会社から借りることも可能です。
しかし途中で解約した場合には、支払った保険料より解約返戻金が安くなる、もしくは返戻金が受け取れない可能性も。
利率固定型の場合は、インフレによって資産価値が低くなるなどのデメリットも考えられます。
しかし一生涯保障が続く、解約返戻金が受け取れるという点は掛け捨て型にはない大きなメリットだと言えるでしょう。
「掛け捨て型」と「貯蓄型」それぞれのメリットから分かったおすすめな人
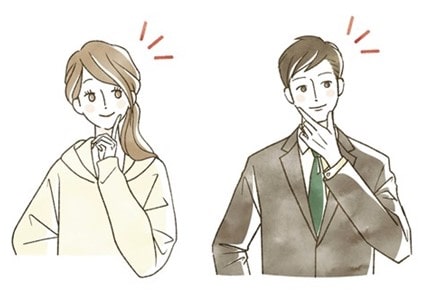
「掛け捨て型」と「貯蓄型」の生命保険の特徴やメリット・デメリットを比較してきました。
次にそれぞれの保険がどういう方に向いているのかを紹介します。
| 「掛け捨て型」がおすすめな人 | 「貯蓄型」がおすすめな人 |
| ・保険料を抑えたい人 ・少ない保険料で大きな保障を得たい人 ・定期的に保険の見直しをしたい人 ・保障と貯蓄は別に考えたい人 | ・保険料を無駄にしたくない人 ・保障と貯蓄の両方を備えたい人 ・途中解約の可能性が低い ・貯蓄が苦手な人 |
掛け捨て型と貯蓄型はそれぞれ特徴が異なるため、目的によっておすすめな人が変わってくるでしょう。
生命保険を検討する際は目先の保険金や解約返戻金にとらわれがちですが、決してそれだけではありません。
生涯の資金計画を立てた上で、必要な保障内容や保険金を把握することが大切です。
保険会社やファイナンシャルプランナーに相談しながら、自分や家族にとってどれがいいのかを検討しましょう。
生命保険がおすすめの理由まとめ
今回は生命保険の種類やおすすめの理由、選び方などについて紹介しました。
生命保険にはたくさんの種類があり、商品によってさまざまな保障内容があります。
必要な保障は家族構成や年齢、ライフステージによって異なるため、まずは加入の目的を明確にすることが大切。
自分や家族にとってどのようなリスクがあるのか、それに対してどんな保険が必要なのかを知るところからスタートしましょう。
どんな生命保険が必要か分からない方は、ぜひファイナンシャルプランナーに相談してみてください。
これを機に家族や親しい人を守る生命保険への加入や見直しを、検討してみてはいかがでしょうか。